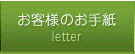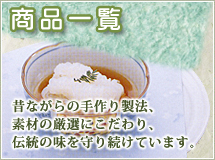こんにゃくの歴史
皆さんは、コンニャクがどのように造られるかご存知でしょうか?
コンニャクは、コンニャクの芋を蒸してすり潰し石灰水(アルカリ水)を混ぜて煮込むと固まりコンニャクになります。現在は凝固剤として石灰を使用しますが、昔はわらを燃やした炭を水に溶かし、ろ過したものを凝固剤として使用していました。
コンニャクの芋は、非常にエグみが強く、とてもそのままでは食べることは出来ません。私も一度生のままかじった事がありますが、半日ぐらい喉の奥がイガイガして大変でした(* *)
このような芋を1000年以上前の人は灰汁を混ぜてエグみを取り除き食用に考えたのです。今、何の知識も無くコンニャクイモを私の前に出されても、そんな食べ方は全然思いつきません。昔の人には感心させられます。
コンニャクの千年歴史
コンニャクの歴史は古く我が国には中国から仏教の伝来とともに精進料理として伝わったと言われる説や、飛鳥時代の欽明天皇「きんめいてんのう」(539〜571年)聖徳太子が生まれる少し前の頃に朝鮮から伝わった説、又同じく飛鳥時代に遣唐使(630〜894年)が持ち帰ったという説があります。初めの頃は医薬用として珍重され貴族や王族しか食べられなかったのですが、やがて一般の人の食べ物になっていったようです。
コンニャクの名が載っている日本で一番古い書物は平安時代の歌人、源順「みなもとのしたごろう」が書いた「倭名類聚抄」(わみょうるいじゅしょう)(931〜937年)という辞書でこの中に次のように述べられています。
「蒟蒻、其の根は白く、灰汁をもって煮れば、すなわち凝成す。苦酒(酢)をもってひたし、これを食す。」
(コンニャクの根っこは白く、灰から作ったアク汁で煮ると固まり、酢をつけて食べる。)
この記述から、当時すでにコンニャク芋を灰汁で処理することで食用となることが知られていたようです。その後平安時代の「拾遺和歌集」(しゅういわかしゅう)(1005〜1007年)の中にもコンニャクが歌われています。
コンニャクが一般に知られ常食化したのは鎌倉時代以降と思われます。たとえば「庭訓往来」(ていきんおうらい)(1330年)と言われる当時の教科書には、コンニャクをたれ味噌で煮て、唐伝来の間食をしたと記されています。室町時代には点心(菓子や間食、軽食)として利用され、戦国時代には豆腐や納豆とともに食用として食べられていました。しかし庶民の食品として広く普及したのは江戸時代からで、詩人として有名な松尾芭蕉も好んで食べたと言われ、詩にもうたわれています。
「こにやくの刺身も些し うめの花」
(こんにゃくの刺身も少し 梅の花) 芭蕉50歳(1693年)
その後1776年の水戸藩領(現 茨城県大宮市)の中島藤右衛門がコンニャクの芋を薄切りにして乾燥させ粉末にする技術を発明しコンニャクが広まってきました。この時代には「蒟蒻珀珍」(1846年)という料理書も発行されています。
もともとは海外から伝わったとされていますが、1000年以上にわたって代々受け継がれてきた日本ならではの食材それが “コンニャク” なのです。